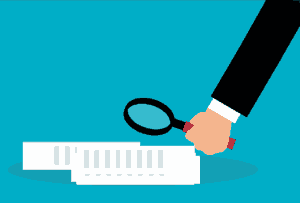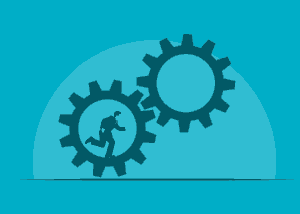- 年金受給者も債務整理は可能(返済計画の実現性が重要)
- 2007年以前からの取引は過払い金の可能性あり(先に確認)
- 任意整理で無理なら個人再生(減額)か自己破産(免責)を検討
年金のみで生活している中で、借金の返済に追われている方は少なくありません。
もし毎月の返済が難しい状況なら、債務整理によって返済負担を軽減できます。
本記事では、年金受給者でも利用できる債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)を、司法書士の視点でわかりやすく解説します。
あわせて、取引が長い方に起こりやすい過払い金への対応も紹介します。
参考元:債務整理-東京司法書士会
年金受給者でも任意整理は可能?
- 年金を受給していますが任意整理をすることはできますか?
-
任意整理後に分割返済をしていくことができる場合は、年金受給者でも任意整理をすることができます。
- 任意整理の内容
- 利息をカットし、元金だけを3~5年(36〜60回)で分割返済する手続き
- 利用できる条件
- 任意整理後の返済額を、毎月無理なく支払えること
- 返済計画が赤字にならないことが必須条件
- 返済額の計算方法
- 借入額 ÷(36〜60)= 毎月の返済額
毎月の返済額シミュレーション
任意整理後は36回~60回の分割払いになるので、借入額を36~60で割ることでおおよその任意整理後の毎月の返済額を算出することができます。
| 借入額 | 36回払い (3年払い) | 60回払い (5年払い) |
|---|---|---|
| 30万円 | 約8,300円 | 約5,000円 |
| 60万円 | 約16,600円 | 約10,000円 |
| 100万円 | 約27,700円 | 約16,600円 |
年金受給者:任意整理をした事例
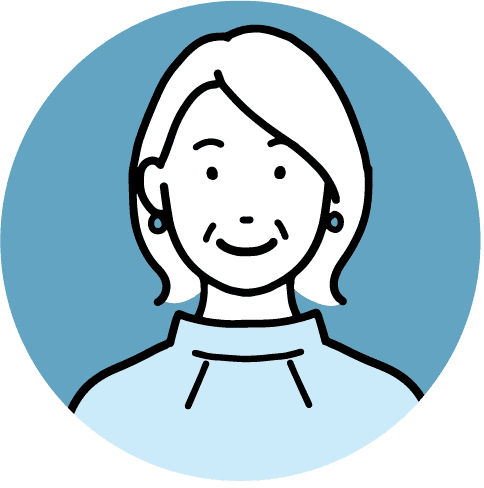 60代 女性
60代 女性年金で生活しながら借金の返済追われていました。司法書士に依頼して任意整理をしたところ、毎月の返済額が減り生活費を確保できるようになりました。
任意整理が可能かの判断基準
- 年金収入 − 生活費(住居費・食費・医療費など)
- 差し引いた残りの金額で、任意整理後の返済額を無理なく支払えるかを確認
任意整理ができないパターンについては以下の記事で詳しく解説しています。
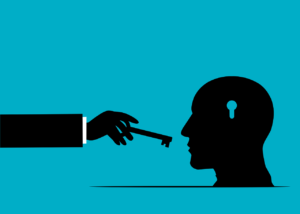
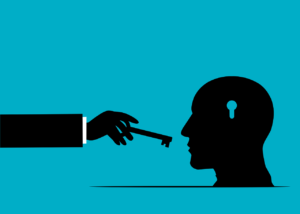
任意整理でも返済が難しい場合の選択肢
- 任意整理では返済ができない時はどうすればいいですか?
-
任意整理ができない場合は、個人再生か自己破産を検討するべきです。
個人再生をすれば借金が減額され、自己破産をするとすべての借金の支払いをする必要がなくなります。
年金収入から生活費を差し引くと返済が難しい場合、任意整理は利用できません。
そのような場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理の手続きを検討する必要があります。
個人再生(借金の大幅減額)
- 借金を法律の基準に沿って大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度
- 年金のような安定収入があれば利用可能
- 1500万円未満の借金
- 借金額の5分の1
- 減額後の金額が100万円未満の場合は100万円
- 1500万円以上3000万円未満の借金
- 300万円
- 3000万円以上5000万円未満の借金
- 借金額の10分の1
自己破産(借金の支払い義務が免除)
自己破産は、すべての借金の支払い義務が免除される手続きです。
返済がまったくできない状況でも、生活再建のために利用できる最終手段です。
自己破産には職業制限や財産の処分、免責不許可事由等があるので、事情によって自己破産ができない人は個人再生を検討するべきです。
取引が長い人は過払い金を確認すべき
- 債務整理をする前に何かしておいたほうがいいことはありますか?
-
取引が長い人は、任意整理をする前に過払い金があるか確認するべきです。
過払い金が発生していれば、借金は無くなるので債務整理をする必要もなくなります。
- 過払い金とは
- 法律(利息制限法)の上限を超える利息で取引をしていた場合に発生するもの
- 発生しやすい時期
- 2007年以前に借入を始めた人:過払い金が発生しやすい
- 2008年以降に借入した人:過払い金が発生する可能性は低い
多くの貸金業者は2007年前後に法律内の利息に見直しているため、2007年以前に借入を始めた人ほど発生しやすい傾向があります。
利息制限法の上限金利
| 借入額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上〜100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
いつから借りたかを確認する方法については以下の記事で詳しく解説しています。


引き直し計算で減額や完済扱いになるケース
引き直し計算とは?
- 実際に払った利息を、法律上の上限利率に引き直して再計算すること
- 例:50万円を年27%で借入している場合
- 利息制限法内の18%で計算し直す
過去の高金利部分を法定利率に置き換えて再計算(引き直し計算)すると、元金の減りが早まります。
その結果、残高が減額されたり、すでに完済扱いとなって過払い金が生じることがあります。
年金で返済中:過払い金が返金された事例
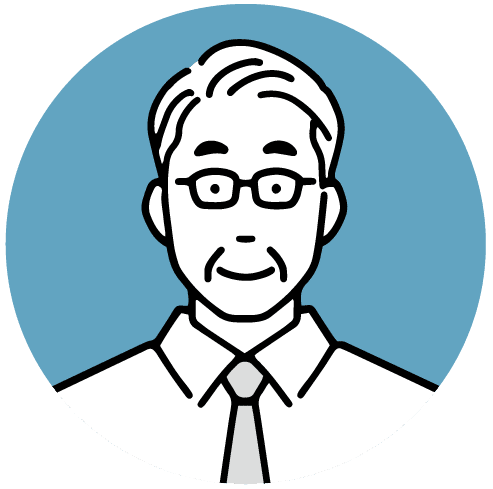
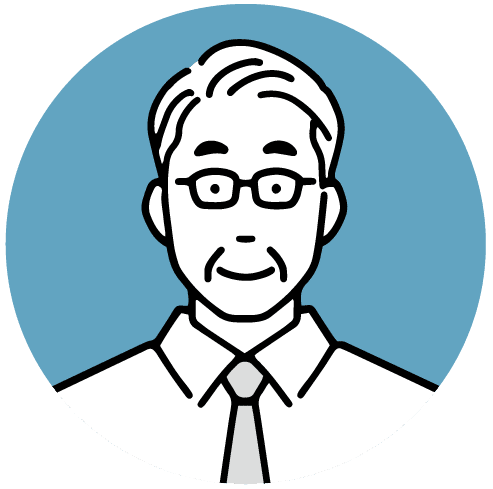
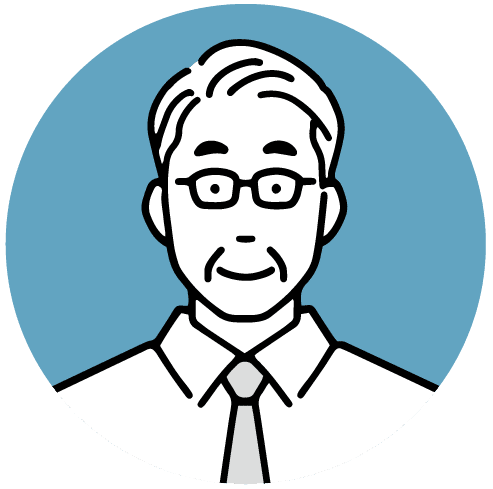
2005年から借りて最近は年金から返済していました。返済が難しくなってきたので司法書士に相談したところ、借金がなくなりお金が戻ってきました。
例:50万円の借入がある場合
- 借金が0円になり、過払い金が20万円発生
- 借金が消えて過払い金請求で返金へ
- 残高が30万円に減額
- 減額後の残債を任意整理(利息カット・36〜60回で分割払い)
借金返済中の過払い金請求については以下の記事で詳しく解説しています。


よくある質問
障害年金や遺族年金を受給している場合でも債務整理はできますか?
はい。老齢年金に限らず、障害年金や遺族年金などでも手続きの利用は可能です。
年金以外に収入がないと、個人再生は利用できませんか?
個人再生は「継続的に返済できる安定収入」が必要です。
年金収入であっても裁判所に認められれば利用できます。
生活保護と年金を併用している場合でも債務整理は可能ですか?
生活保護と併用している場合は自己破産が選ばれることが多いです。
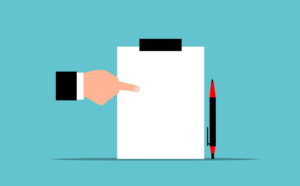
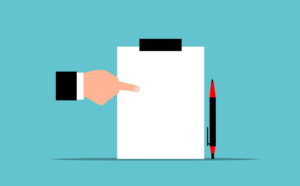
債務整理をすると税金や国民健康保険料の支払いも免除されますか?
いいえ。税金や社会保険料は債務整理の対象外です。
別途支払いが必要です。


まとめ:年金受給者でも債務整理は可能
- 年金受給者も任意整理はできる
- 任意整理後に毎月の返済ができることが条件
- 任意整理が難しい場合は個人再生(減額)か自己破産(免責)を検討
- 2007年以前からの取引は過払い金の可能性あり
- 債務整理をする際に過払い金の調査がされます
司法書士からのアドバイス
- 債務整理を検討する際は、収支を必ず具体的に計算することが重要です
- 感覚的に「払えそう」と思っても、数字にすると赤字になるケースが多くあります
- 医療費や介護費など将来的に支出が増える可能性も考慮して計画を立てましょう
- 取引が長い人はまずは過払い金の有無を確認
- その結果に応じて任意整理・個人再生・自己破産を選択することが大切です
不安がある場合は、司法書士や弁護士に早めに相談し、実際の返済計画を一緒にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。