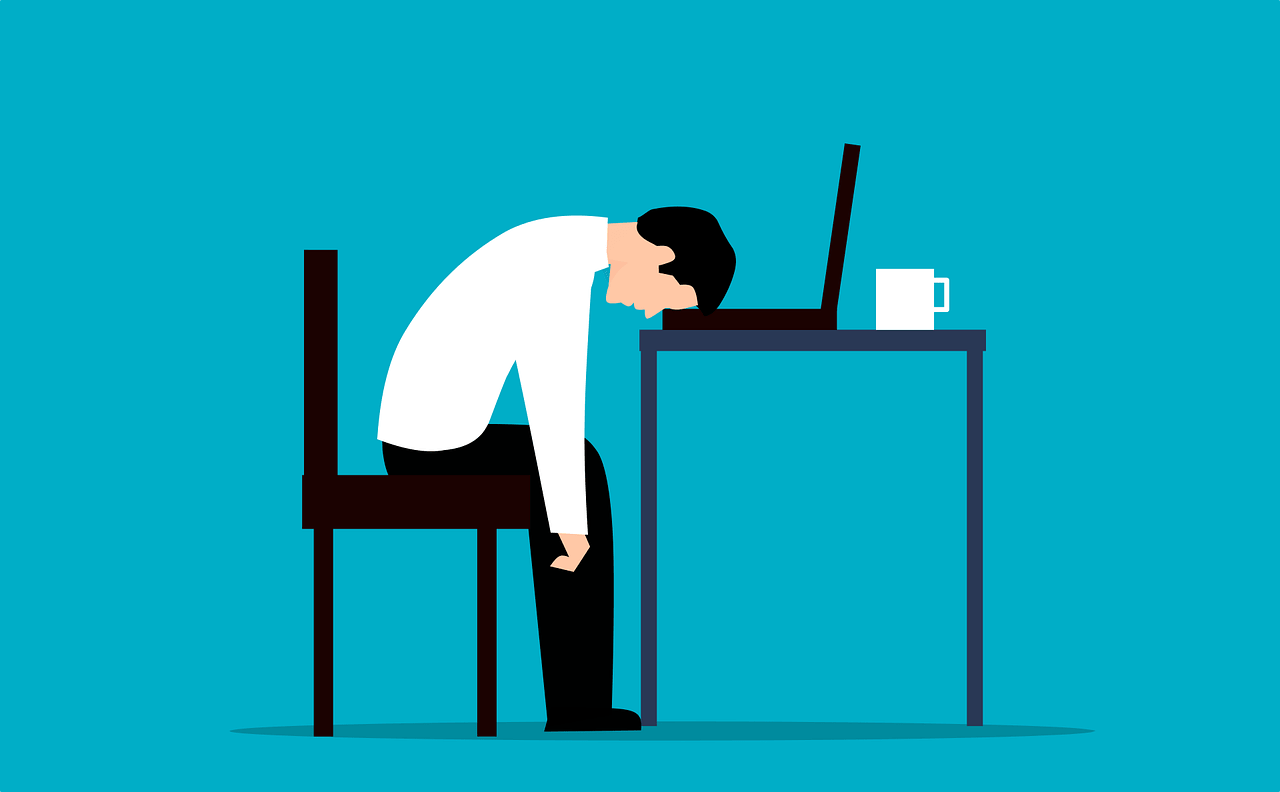借金を残して家族が亡くなってしまっても、長期間返済を続けていた場合は「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金請求をする前に亡くなっても、過払い金返還請求権は相続財産として引き継がれるので、相続人から請求することができます。
借金の相続・相続放棄を検討する前に、必ず過払い金の有無を確認しましょう。
過払い金があるか確認する方法は?何から始めればいいか?相続人からの過払い金請求についての注意点まで解説しています。
参考元:過払い金を請求できるケースとは?|しほたんと学ぶ法律教室-東京司法書士会
【結論】過払い金は相続財産|相続人も請求できます
- 家族が過払い金請求をしないまま亡くなったら、相続人から過払い金請求はできますか?
-
過払い金請求権も相続されるので、相続人から請求をすることができます。
親や家族が長年消費者金融やカードローンを利用していた場合、払いすぎた利息(過払い金)が発生している可能性があります。
過払い金は「財産」として扱われ、相続の対象になります。
相続人の範囲と相続割合(配偶者・子/父母/兄弟姉妹)
相続人の範囲は民法で定められており、次の順位で決まります。
- 配偶者と子ども
- 子が亡くなっていれば孫
- 配偶者と父母
- 父母が亡くなっていれば祖父母
- 配偶者と兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪
上記①の子供や孫等がいなければ②の父母や祖父母等が相続人になります。
②の父母等がいなければ③の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人ごとで相続される割合も異なります。
| 相続人 | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者+子供 | 配偶者 1/2、子 1/2 (子2人なら各1/4) |
| 配偶者+父母 | 配偶者 2/3、父母 1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |
夫の遺産1000万円、妻と2人の子供がいるケース
妻=500万円、子供1人あたり250万円になります。
過払い金が発生している可能性の見分け方
- 利息制限法を超える金利で借入をしていた
- 借入開始時期が2007年以前
- キャッシング(現金の借入)をしていた
金利が法定上限を超えていないか
下記の上限を超える利息で返済していた場合、過払い金が発生している可能性があります。
| 借入金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上~100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
2007年以前の借入かどうか(高金利時代の目安)
書類がなく利息が何%だったのかわからなくても、2007年よりも前からの借入であれば過払い金が発生している可能性があります。
過払い金はキャッシングで発生するので、ショッピングのリボ払いや銀行からの借入では発生しません。
借金がなくなって過払い金が発生した事例
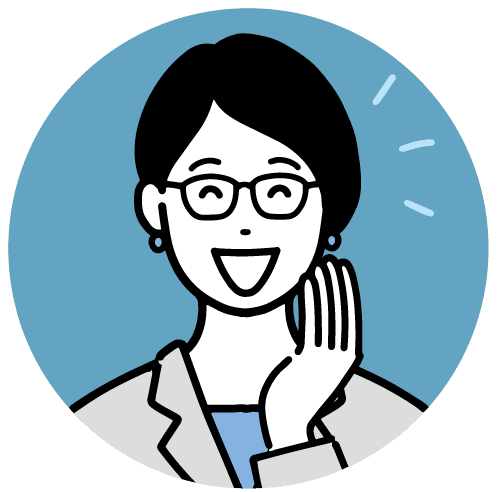 50代 女性
50代 女性亡くなった父の借金を司法書士に相談したところ、過払い金が発生していると判明。結果的に借金はなくなってさらにお金が戻ってきました。
過払い金の仕組みについては以下の記事でも詳しく解説しています。
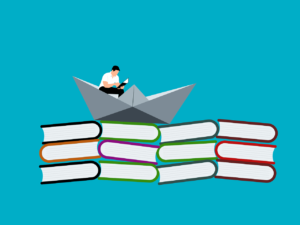
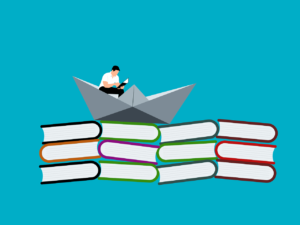
借入先や取引年数がわからないときの調査手順
借入の開始時期が不明な場合でも、取引履歴を取り寄せれば確認が可能です。
以下の流れで進めるとスムーズです。
まずは書類で確認できるかチェック
- 貸金業者との契約書
- 借入を開始した日付や契約時の金利が記載されている
- 支払明細
- 取引をしていた日付を確認できる、契約日や金利が確認できる場合もある
- 督促書
- 返済が遅れたときに届く通知で、業者名や借入条件が記載されていることがある
- カード(ローンカード・クレジットカード)
- 過払い金請求の対象業者を特定できる
- 引き落とし通帳
- 引き落とし名義に貸金業者の名前が表示され、過払い金請求の対象業者を特定できる
金利がわかれば:その利率が法律の上限を超えているかどうかで、過払い金が発生しているか確認できます。
契約日や取引日がわかれば:2007年以前からの借入かどうかを判断でき、その時期であれば過払い金が生じている可能性があります。
書類がない場合は「取引履歴」を請求
貸金業者に連絡して、取引履歴を取り寄せできます。
カスタマーセンターに「相続財産の調査のために取引履歴を取得したい」と伝えれば大丈夫です。
取引履歴でわかること
- 借入を開始した時期
- 借入・返済の金額と日付
- 契約時の利息
- 貸金業者によって利息は記載されていない
| 確認できること | 内容 |
|---|---|
| 過払い金が発生しているか | 金利が利息制限法を超えていたかどうか |
| 正確な過払い金額 | 引き直し計算により算出 |
取引をしていた業者名が不明なら信用情報を取得する
書類もなく、取引をしていた業者名が確認できない場合は、信用情報機関から信用情報を取り寄せれば確認できることがあります。
過払い金の計算方法
- 取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて再計算(引き直し計算)を行う
- この計算によって過払い金の有無や金額が確定する
引き直し計算については以下の記事でも詳しく解説しています。


専門家に依頼するメリット
弁護士や司法書士に依頼すれば、以下を代理で行ってもらえます。
- 取引履歴の取り寄せ
- 引き直し計算
- 過払い金の請求手続き
専門家に任せれば、手間を減らし、請求漏れや計算ミスを防げます。
ポイントまとめ
ポイントは「書類がなくても取引履歴を取得して過払い金の請求はできる」ということです。
取引年数が不明な場合は、まず業者に履歴開示を求めましょう。
弁護士や司法書士に依頼をすれば、取引履歴の取得から計算まで、弁護士や司法書士が代理人として行うこともできます。
いつから借りたかを確認する方法については以下の記事でも詳しく解説しています。


相続人が過払い金を請求する方法
- 相続人が複数いる時は、誰が過払い金請求をするんですか?
-
下記の方法があります。
- 遺産分割協議をして相続人の一人から請求する方法
- 相続人全員での請求する方法
- 相続人一人で、自己の法定相続分のみを請求する方法
相続人が複数いる場合の対応方法は次のとおりです。
- 遺産分割協議で代表者が請求
-
遺産分割協議書で合意があれば、一人が代表して請求することも可能です。
- 相続人全員で請求
-
法定相続分に従って過払い金を分け合うことが可能です。
- 一部の相続人のみで請求
-
相続人の一人から自分の相続分のみの過払い金を請求する方法。
相続人が何人かいるのであれば、相続人全員から請求するか、遺産分割協議を行って一人の方から請求する方法が一般的です。
他の相続人と連絡が取れない等の事情がなければ基本的には全員から、または遺産分割をして請求を行うことになります。
相続人からの過払い金請求で必要になる書類
- 相続人から過払い金請求をするには、どのような書類が必要になりますか?
-
まずは相続が発生していることを証明するために、戸籍が必要になります。
誰が相続人になるのかを確認するために、亡くなった人の戸籍謄本は生まれた時まで遡った戸籍を集める必要があります。
相続人からの過払い金請求では、以下の書類を揃える必要があります。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要
- 相続人が誰なのかを確認するために必要になる
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人になる人が死亡していないか等を確認するため
- 遺産分割をした場合
- 遺産分割協議書(印鑑証明書も必要)
- 相続放棄した相続人がいる場合
- 相続放棄申述受理通知書
- 遺言書がある場合
- 遺言書
また、相続登記や金融機関への提出等、複数の手続きに使用する場合は、法定相続情報一覧図を作成すれば手続きがスムーズになります。
戸籍の収集まで司法書士に依頼をした事例
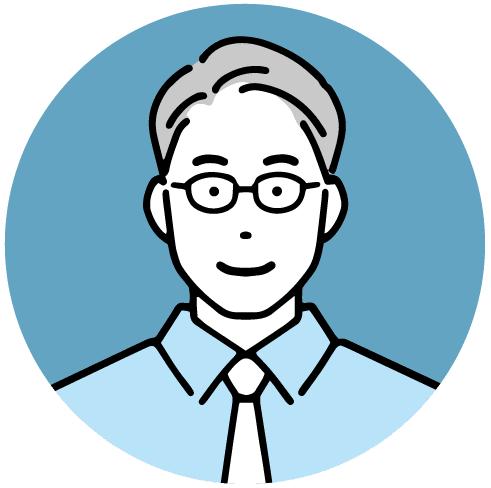
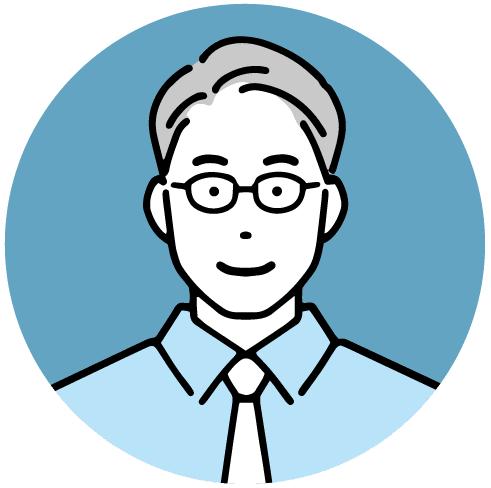
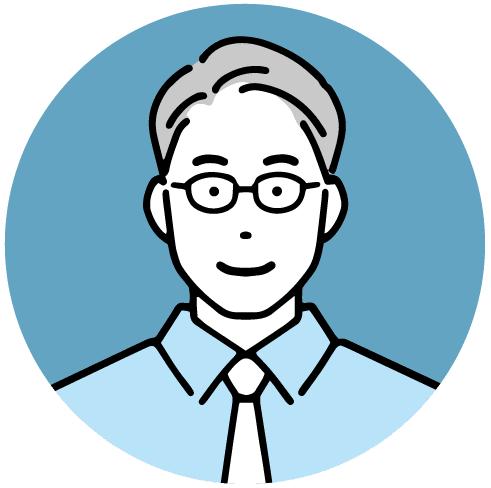
父は本籍地が何度も変わっていたため、戸籍集めが大変でした。司法書士に依頼したら代わりに戸籍を集めてもらえたので、手間も時間も大幅に省けました。
相続放棄と過払い金の関係(単純承認の注意)
- 相続放棄を検討していますが、過払い金は請求できなくなりますか?
-
過払い金請求をすると、相続放棄はできなくなります。
財産よりも借金が多い場合は相続放棄を検討すべきですが、相続放棄には条件があります。
- 相続があったことを知った時から3か月以内にすること
- 単純承認に該当する行為をしていないこと
過払い金請求をすると相続放棄はできない
過払い金に期待していたけど、発生していなくて借金だけ残ってしまうこともあり得ます。
逆に相続放棄を検討していたが、調査してみたら過払い金が多額で、相続放棄をする必要がなくなることもあります。
判断の手順(調査 → 判断 → 手続き)
ポイントは「過払い金の有無を確認してから判断すること」です。
誤って請求してしまうと相続放棄ができなくなるので、調査 → 判断 → 手続きの順で進めましょう。
過払い金があり相続放棄の必要がなくなった事例
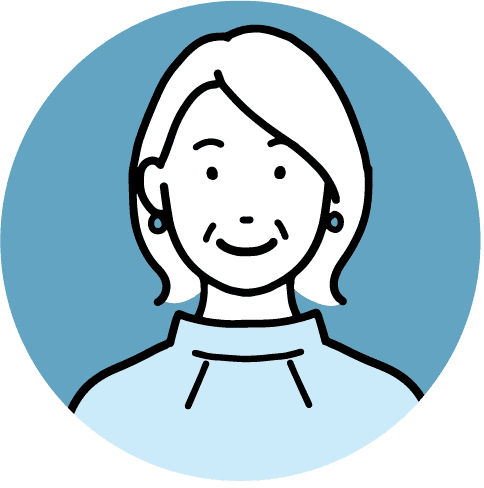
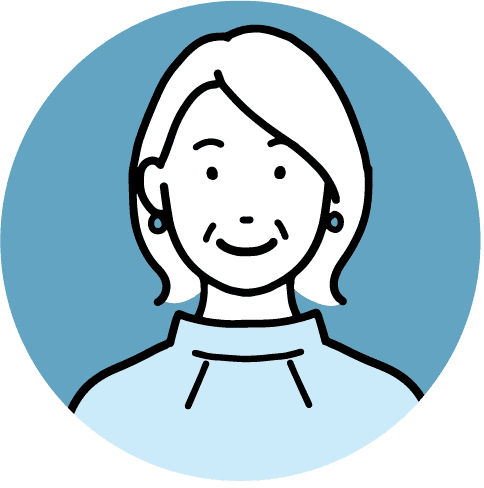
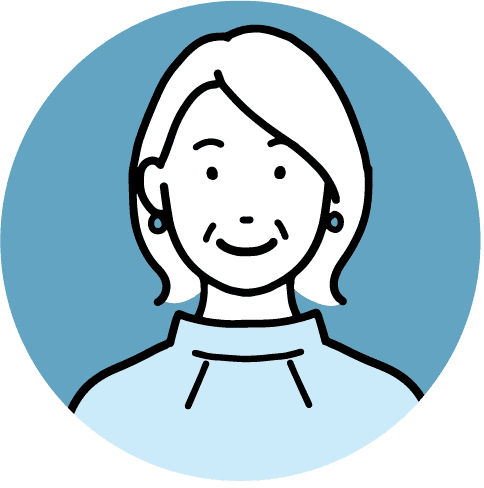
父が借金を残して亡くなったので相続放棄を考えました。念のため司法書士に調査をしてもらったら過払い金が見つかりました。放棄していたら大きな財産を失っていたと思います。
3か月に間に合わないときの「期間伸長」の申立て
調査に時間がかかり、3か月を経過しそうな場合は、裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
調査結果別の対応早見表
| 調査結果 | 対応方法 |
|---|---|
| 過払い金がない | 借金が残っているなら 相続放棄を検討する |
| 過払い金 > 借金 or 借金なし | 過払い金を請求する |
| 借金 > 過払い金 | 財産がなければ 相続放棄を検討する |
| 自宅など放棄できない財産あり | 相続放棄ができないなら 債務整理も検討 |
過払い金だけを回収して、借金を放棄することはできません。
「財産と借金すべてを引き継ぐ」か「すべて放棄するか」のどちらかになります。
相続放棄ができない場合の債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。


過払い金の時効とタイムライン
過払い金の時効は、最後の取引から10年、または過払い金が請求できることを知ってから5年です。
亡くなってから10年ではありません。
亡くなる前に既に完済していた場合は、特に時効に注意が必要になります。
途中完済(分断)がある場合の注意
また、取引の途中で完済したことがあると、取引の分断で途中完済時点までの過払い金が時効になることもあります。
過払い金の時効については以下の記事でも詳しく解説しています。


手続きの全体像(ステップ一覧)
借金や過払い金がある可能性があるなら財産調査を開始
- 調査対象
-
- 借金(消費者金融・クレジットカードなど)
- 過払い金(払いすぎた利息)
- 預貯金
- 不動産、自動車など
- 調査方法
-
- 契約書や明細書
- 通帳の引き落とし履歴
- カード
- 信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)から開示請求
- 利息が法定金利を超えていれば過払い金は発生する
- 10万円未満:年20%
- 10〜100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
- 2007年以前からの借入
- 過払い金が発生する可能性が高い
- 確認方法
- 取引履歴を貸金業者から取り寄せ
- 引き直し計算により過払い金額を算出
- 弁護士や司法書士が代行可
- プラスの財産が多い場合(過払い金・預金など)
- 相続を選択し、過払い金請求を進める
- 借金のみ、または借金が財産より多い場合
- 相続放棄を検討する
- 家・土地など放棄できない財産がある場合
- 相続放棄はできないため、債務整理を検討する
- 相続人の優先順位
-
- 配偶者と子供(子が死亡していれば孫)
- 配偶者と父母(または祖父母)
- 配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)
- 相続人が複数の場合
-
- 遺産分割協議で1人に代表させる
- 全員で請求
- 自己の相続分のみの請求
- 亡くなった人の戸籍(出生〜死亡まで)
- 相続の発生と相続人を証明するために必要
- 相続人全員の現在の戸籍
- 誰が相続人かを確認するために必要
- 遺産分割協議書+印鑑証明書(協議をした場合)
- 誰が請求者となるかを確定するために必要
- 相続放棄申述受理通知書(ある場合)
- 相続放棄をした相続人がいることを証明するために必要
- 遺言書(ある場合)
- 相続の内容を確認するために必要
- 最後の取引から10年が過払い金の時効
- 完済してから時間が経っている場合は要注意
過払い金請求の流れについては以下の記事でも詳しく解説しています。


よくある質問(FAQ)
相続放棄をした後でも過払い金は請求できますか?
できません。過払い金も含めてすべて放棄したことになります。
遺言書に「特定の相続人に全財産を相続させる」と書いてある場合、過払い金も含まれますか?
含まれます。過払い金返還請求権は相続財産の一部なので、特定の相続人に全財産を相続させる旨の遺言がある場合は過払い金も含まれることになります。
相続人同士でトラブルになった場合はどうなりますか?
誰が請求するか、分配割合で争いがある場合は家庭裁判所の遺産分割調停等で解決する方法があります。合意ができなければ代表者からの請求はできません。
相続放棄をした相続人が、後から過払い金を請求できますか?
できません。相続放棄をすると、過払い金を含むすべての財産を放棄した扱いになるためです。
まとめ/司法書士からのアドバイス
相続が発生したときの基本的な流れは次のとおりです。
- まずは財産調査が最優先
- プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握することが必要です。
- 借金が多い場合
- 相続放棄をすることで、借金を引き継がずに済みます。
- 自宅や土地がある場合
- 相続放棄ができないため、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する流れになります。
- 相続放棄の期限に注意
- 「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
- 調査は専門家に依頼可能
- 戸籍収集や取引履歴の開示などは手間がかかるため、司法書士・弁護士に任せることでスムーズに進められます。
まずは調査、迷ったら専門家へ
相続と過払い金請求は「相続放棄ができるかどうか」「債務整理が必要かどうか」の判断がとても重要になります。
- 過払い金が発生しているのに相続放棄してしまうと、本来取り戻せるお金を失ってしまいます。
- 逆に、安易に過払い金を請求すると、相続放棄ができなくなるリスクもあります。
そのため、相続放棄の期限(3か月)に間に合うように、まずは財産調査を行いましょう。
不安がある場合は、専門家に依頼して「調査→請求→放棄・整理」の判断を一緒に進めることをおすすめします。